最新の医師転職・求人・募集サイトを、口コミ&評判つきで比較・ランキングします。

トップページ > 医師を取り巻く問題「生活の為に無理する若手医師」
医師と言えども転職が当たり前の時代になってきました。その理由は様々ですがやはり、「これからのキャリアプランを考えて」、「年収をもう少し増やしたい」、「仕事に忙殺されていて、もう少し自分や家族との時間がほしい」と言った、誰もが納得できる理由が多いように感じます。一度しかない人生ですから、悔いのない生き方・働き方を選びたいものです。転職に悩んでいる先生方か、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
医師を取り巻く問題
「生活の為に無理する若手医師」
医師を取り巻く問題
- トップページ
- 医師転職・求人・募集サイト比較
- 医師を取り巻く問題
-
- 過酷労働が常態化する勤務医
- 労働基準法では規制できない
- 新臨床研修制度で医師が偏在
- 生活の為に無理する若手医師
- 過酷労働で発生する医療ミス
- 医療事故で逮捕された医師
- 医療訴訟が医師を追い詰める
- 患者を診るのが医師という期待
- 医師の厳しい上下関係
- 超高齢社会や業務の変化
- 医師不足の嘘と真実
- 国の医師負担軽減策は不十分
- 離職する医師と、そうならない医師
- 異常な労働環境
- 仕事が好きだから起きる過剰適応
- 患者が人質だから辞められない
- 38歳、内科医の証言
- 自分の望む医療とのギャップ
- 医局を離れるという選択肢も
- 多忙さがスキルアップを奪う
- 28歳、内科医の証言
- スタッフ、患者との信頼関係を築けない医師
- 医師を追い詰める同僚や上司からのいじめ
- 看護師との関係悪化で医療が崩壊
- 患者さま気取りのモンスター患者に疲弊
- 勤務先との軋轢で心が折れる医師
- 経営優先で、不正な診療をさせるブラック病院
- トラブルをすべて医師の責任にする病院
- 37歳、外科・麻酔科医の証言
- 育児・介護などのために離職を選ぶ医師
- 保育所の不備や、同僚の無理解に悩む女性医師
- 今は介護も、医師離職の大きな原因に
- 35歳、内科医の証言
- 医師が笑顔で働き続けるために、今すべきこと
- 過酷な労働環境を「人助け」と思わせない(1)
- 過酷な労働環境を「人助け」と思わせない(2)
- 適切な勤怠管理を行う
- 医師に健康診断を受診させる(1)
- 医師に健康診断を受診させる(2)
- 医師自身がキャリアプランを考える(1)
- 医師自身がキャリアプランを考える(2)
- 医局以外のキャリアも用意する(1)
- 医局以外のキャリアも用意する(2)
- 幅広い視野で、活躍の場を用意する(1)
- 幅広い視野で、活躍の場を用意する(2)
- 医師と医療機関のミスマッチをなくす(1)
- 医師と医療機関のミスマッチをなくす(2)
- 医師と医療機関のミスマッチをなくす(3)
- 周囲の人とのコミュニケーションを重視する(1)
- 周囲の人とのコミュニケーションを重視する(2)
- 患者教育で医療を救う(1)
- 患者教育で医療を救う(2)
- 医師一人ひとりの声をすくい上げる(1)
- 医師一人ひとりの声をすくい上げる(2)
- 医師の健康管理は看過できないテーマ
- 医師が気兼ねなく休める環境が大切
- 医師の過重労働を軽減するには
- 医療事故や患者からの暴力・クレームには組織で
- 医師が働きやすい病院には、患者も集まる
- 大切なのは医師の公平・公正な給与体系
- 勤務先を選ぶことは止めることができない権利
- 医師にとって地方の優位性も十分にある
- 産婦人科、小児科、麻酔科、外科の魅力
- 漫然とした病院経営で立ち行かなくなるのは必然
- 医療機関が生き残っていく確実な道
- 機能的な診療を実現するのは、医療と経営の分離
- 超高齢社会で、求められる医療も変わる
- 医師が「健康で長く働ける」勤務スタイル
- 女性医師の力を活かす
- 医療機関が女性医師の環境を鑑み口を出すべき
- 女性医師活用が職場環境や経営の改善につながる
- 日本の主治医制度の問題点
- チームで診療にあたるというスタイル
- フランスでは1ヶ月のバカンスに行く医師
- 世界一の医療を支える医師の献身と長時間労働
- 日本の中高年男性の自殺は世界トップクラス
- 医師とポジティブ・オフ運動
- 医師紹介業が果たす役割(1)
- 医師紹介業が果たす役割(2)
目次
- トップページ
- 医師転職・求人・募集サイト比較
- 医師転職アドバイス
-
- 医師転職アドバイス「医師転職支援会社の注意点は?」
- 医師転職アドバイス「医師転職会社のメリットは?」
- 医師転職アドバイス「医師転職会社のデメリットは?」
- 医師転職アドバイス「医師転職会社利用 5つのケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職ノウハウ〜変化する状況」
- 医師転職アドバイス「医師転職ノウハウ〜ご家族の意見」
- 医師転職アドバイス「医師転職ノウハウ〜優先順位」
- 医師転職アドバイス「うまい話にはご注意を」
- 医師転職アドバイス「医師転職の落とし穴」
- 医師転職アドバイス「医師転職面談の流れ、コツ、注意点」
- 医師転職アドバイス「医師転職面談から決定までの流れ」
- 医師転職アドバイス「医師転職で成功するには?」
- 医師転職アドバイス「医師転職:産婦人科医のケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職:整形外科医のケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職:循環器内科医のケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職:心臓外科医のケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職:精神科医のケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職:耳鼻咽喉科医のケース」
- 医師転職アドバイス「医師転職:リハビリ科医のケース」
- 医師転職アドバイス「転職先として魅力的な病院とは」
- 医師転職アドバイス「医師転職に大切なのは長期的視野」
- 医師転職アドバイス「外科系教授が転職を決断した理由」
- 医師転職アドバイス「医局人事の閉塞感」
- 医師転職アドバイス「人生の岐路を活かせる人とは?」
- 医師転職アドバイス「恥ずかしくて言えない転職理由」
- 医師転職アドバイス「医局派遣医の思い込み」
- 医師転職アドバイス「医局を退局された医師のアドバイス」
- 医師転職アドバイス「医師の退局時の不安」
- 医師転職アドバイス「医局派遣先とのズレ」
- 医師転職アドバイス「リスクの少ない医師の生き方」
- 医師転職アドバイス「医師の最大のリスクヘッジ」
- 医師転職アドバイス「医師のマネジメントの重要性」
- 医師転職アドバイス「医師自らマネジメントする方法」
- 医師転職アドバイス「医師の価値を高める3つの方法」
- 医師転職アドバイス「若手医師の指導の難しさ」
- 医師転職アドバイス「医師の前向き転職、後向き転職」
- 医師転職アドバイス「救急医療と大学医局の崩壊」
- 医師転職アドバイス「医師のための医師という道」
- 医師転職アドバイス「転職の成功と失敗」
- 医師転職アドバイス「病院が感じる医師転職傾向」
- 医師転職アドバイス「医師募集における病院の事情」
- 医師を取り巻く問題
-
- 過酷労働が常態化する勤務医
- 労働基準法では規制できない
- 新臨床研修制度で医師が偏在
- 生活の為に無理する若手医師
- 過酷労働で発生する医療ミス
- 医療事故で逮捕された医師
- 医療訴訟が医師を追い詰める
- 患者を診るのが医師という期待
- 医師の厳しい上下関係
- 超高齢社会や業務の変化
- 医師不足の嘘と真実
- 国の医師負担軽減策は不十分
- 離職する医師と、そうならない医師
- 異常な労働環境
- 仕事が好きだから起きる過剰適応
- 患者が人質だから辞められない
- 38歳、内科医の証言
- 自分の望む医療とのギャップ
- 医局を離れるという選択肢も
- 多忙さがスキルアップを奪う
- 28歳、内科医の証言
- スタッフ、患者との信頼関係を築けない医師
- 医師を追い詰める同僚や上司からのいじめ
- 看護師との関係悪化で医療が崩壊
- 患者さま気取りのモンスター患者に疲弊
- 勤務先との軋轢で心が折れる医師
- 経営優先で、不正な診療をさせるブラック病院
- トラブルをすべて医師の責任にする病院
- 37歳、外科・麻酔科医の証言
- 育児・介護などのために離職を選ぶ医師
- 保育所の不備や、同僚の無理解に悩む女性医師
- 今は介護も、医師離職の大きな原因に
- 35歳、内科医の証言
- 医師が笑顔で働き続けるために、今すべきこと
- 過酷な労働環境を「人助け」と思わせない(1)
- 過酷な労働環境を「人助け」と思わせない(2)
- 適切な勤怠管理を行う
- 医師に健康診断を受診させる(1)
- 医師に健康診断を受診させる(2)
- 医師自身がキャリアプランを考える(1)
- 医師自身がキャリアプランを考える(2)
- 医局以外のキャリアも用意する(1)
- 医局以外のキャリアも用意する(2)
- 幅広い視野で、活躍の場を用意する(1)
- 幅広い視野で、活躍の場を用意する(2)
- 医師と医療機関のミスマッチをなくす(1)
- 医師と医療機関のミスマッチをなくす(2)
- 医師と医療機関のミスマッチをなくす(3)
- 周囲の人とのコミュニケーションを重視する(1)
- 周囲の人とのコミュニケーションを重視する(2)
- 患者教育で医療を救う(1)
- 患者教育で医療を救う(2)
- 医師一人ひとりの声をすくい上げる(1)
- 医師一人ひとりの声をすくい上げる(2)
- 医師の健康管理は看過できないテーマ
- 医師が気兼ねなく休める環境が大切
- 医師の過重労働を軽減するには
- 医療事故や患者からの暴力・クレームには組織で
- 医師が働きやすい病院には、患者も集まる
- 大切なのは医師の公平・公正な給与体系
- 勤務先を選ぶことは止めることができない権利
- 医師にとって地方の優位性も十分にある
- 産婦人科、小児科、麻酔科、外科の魅力
- 漫然とした病院経営で立ち行かなくなるのは必然
- 医療機関が生き残っていく確実な道
- 機能的な診療を実現するのは、医療と経営の分離
- 超高齢社会で、求められる医療も変わる
- 医師が「健康で長く働ける」勤務スタイル
- 女性医師の力を活かす
- 医療機関が女性医師の環境を鑑み口を出すべき
- 女性医師活用が職場環境や経営の改善につながる
- 日本の主治医制度の問題点
- チームで診療にあたるというスタイル
- フランスでは1ヶ月のバカンスに行く医師
- 世界一の医療を支える医師の献身と長時間労働
- 日本の中高年男性の自殺は世界トップクラス
- 医師とポジティブ・オフ運動
- 医師紹介業が果たす役割(1)
- 医師紹介業が果たす役割(2)
- 医学生の進路ガイド
- 医師関連コラム

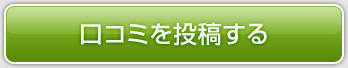
医師の労働環境を考えるときには、医師の報酬にも目を向ける必要があります。
一般には「医師の報酬は高い」「医師は高給取り」というイメージが色濃くあります。しかし若手の勤務医に関しては、決してそれは当てはまりません。
まず2年間の研修期間の平均的な報酬は、年収200万〜300万円程度です。前にも述べたように、新研修制度が導入される前は研修医はほぼ無給で働いていたため、以前に比べれば改善しているのは確かです。
しかし、労働時間の長さや担っている業務の責任の重さを考えると、驚くほど少ないと感じます。むしろ同年代のサラリーマンのほうが、労働に対する報酬としては“割がいい”とさえ思えます。
また、2年の臨床研修を終えた後は、後期研修医(レジデント)という立場で5〜7年ほど勤務を続け、スキルを磨くのが普通ですが、この時期の報酬もおそらく、年収300万〜400万円というケースが多数を占めていると思われます。
ただ後期研修医になると、研修医時代は禁止されていたアルバイトが可能になります。そこで、ひとつの勤務先で長時間労働をこなしたうえに、さらに他の医療機関でアルバイトや非常勤の仕事をこなす若手医師が増加します。
先に挙げた「勤務医の就労実態調査」でも、全体の半数以上の医師が2か所以上の勤務先で業務に従事していると回答しています。それは主となる勤務先で常勤として働く勤務医も同じで、常勤医のほぼ半数が複数の医療機関に勤務しています。
複数の勤務先で働く理由としては、「収入を増やしたいから」が48.1%と、トップを占めており、「ひとつの勤務先では生活自体を営めないから」(34.4%)という切実な声も上がっています。
つまり、若い医師たちの多くは、本来は心身を休める休息や、プライベートの充実に充てるべきオフの時間を、生活のための労働に充てているわけです。
後期研修医の時期を過ぎ、常勤医師として勤務するようになると、ようやく経験に比例して報酬も上がってきます。常勤5、6年目、年齢にして30代後半〜40代になる頃には、平均年収は1000万円を超えるようになりますが、それでも「もっと稼ぎたい」という医師は少なくありません。
医師の場合、結婚して子どもを持つと、子どもを医学部に進学させたいと思う人が多く、教育費を用意したいというニーズが高いようです。あるいは、将来の開業に向けて資金を貯めたいという人もいます。どちらの場合も大きな資金が必要になるため、複数の勤務先のかけもち勤務が続くことになります。
生活費や必要な資金を稼ぐほかにも、勤務先からの指示や医師不足の病院からの要請に応じて複数就業をする医師もいますし、キャリアアップを目的にしている医師もいます。しかし、いずれにせよこの状態では、各医療機関が労基法に則って医師の労働時間を管理したとしても、かけもち勤務をする医師個人の労働時間は少なくなりません。
事実、勤務先数が増えるほど、週あたりの労働時間は増え続け、5か所以上のかけもち勤務をする医師では、週あたりの労働時間は62時間を超え、週に70時間以上働く人も3割を超えています(「勤務医の就労実態調査」)。
まさに骨身を削るようにして働き続ける医師も珍しくなく、その多くが疲弊してしまうのも当然と感じます。
<続く>
医師転職支援会社を調べてみたいと思ったら
>>>医師転職サイト比較ランキング+口コミ評判